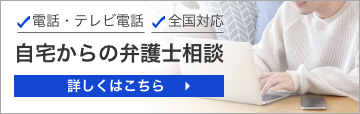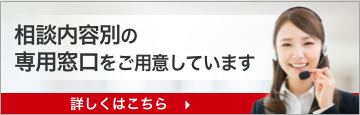間接差別とは? 具体例や予防策、弁護士に相談するメリットを紹介
- 労働問題
- 間接差別

間接差別とは、一見性別に関係のないルールや取り扱いであっても、それを適用することで結果として男女間に不均衡を生じさせる差別をいいます。
平成26年に改正された男女雇用機会均等法では、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種変更をする際に合理的な理由のない間接差別が禁止されています。企業の担当者としては、さまざまな場面で応募者や従業員に対して間接差別にならないよう配慮が必要になります。
特に、令和6年5月13日に地裁判決において間接差別に関する初めての判断が出たことでも注目されていますので、基本的な事項をしっかりと押さえておきましょう。
今回は、間接差別とは何か、具体例や予防策、弁護士に相談するメリットなどについて、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの弁護士が解説します。
1、間接差別とは
そもそも間接差別とはどのようなものなのでしょうか。以下では、間接差別の定義と間接差別に該当するとして会社側が敗訴した裁判例を紹介します。
-
(1)間接差別の定義
間接差別とは、以下の3つの要件を満たす差別をいいます。
- ① 性別以外の事由を要件とする措置
- ② 他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるもの
- ③ 合理的な理由がないときに講じるもの
簡単にいえば、一見性別に関係がないようなルールや取り扱いであっても、それを運用した結果どちらかの性別に不利益が生じるような差別のことです。
-
(2)男女雇用機会均等法における間接差別の対象範囲
男女雇用機会均等法及び厚生労働省令では、合理的な理由なく以下のいずれかの措置をとることは、間接差別として禁止されています。
- ① 労働者の募集または採用にあたって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
- ② 労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更にあたって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするもの
- ③ 労働者の昇進にあたって転勤経験があることを要件とするもの
これらの措置に該当しなければ男女雇用機会均等法違反にはなりませんが、裁判においては、募集・採用、昇進、職種変更以外の場合でも間接差別として違法と判断される可能性がありますので注意が必要です。
-
(3)間接差別に関する初の認定がなされた裁判例|東京地裁令和6年5月13日判決
会社からの従業員への待遇について、間接差別に該当すると初めて認定がなされた裁判例をご紹介します。
【事案の概要】
原告(一般職の女性社員)は、被告会社が総合職に対してのみ社宅制度の利用を認めているのが、男女雇用機会均等法が禁止する間接差別に該当すると主張して、損害賠償などの支払いを求めて提訴しました。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下のような理由から本件社宅制度の運用は間接差別に該当すると判断しました。- 社宅制度を利用できる従業員と利用できない従業員との間で、経済的恩恵の格差がかなり大きい。
- 社宅制度の利用対象となる従業員は、実質的には総合職の従業員である。
- 総合職の男女の比率は、男性の割合が圧倒的に高く、女性の割合が極めて低い。
- 社宅制度の利用を総合職に限定する必要性や合理性は認められない。
- 本件社宅制度は、事実上男性従業員のみに社宅制度の利用を認め、女性従業員に相当程度の不利益を与えていることから間接差別にあたる
- 会社側に計約380万円の損害賠償を命じる
厚生労働省令では、男女雇用機会均等法における間接差別の対象範囲は「労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更」に限定されています。しかし今回の判決は、社宅の貸与という会社が従業員に提供する福利厚生にも判断の枠組みが広げられました。
2、間接差別の具体例
間接差別にあたると考えられる具体例としてはどのようなものがあるのでしょうか。以下では、男女雇用機会均等法が禁止する間接差別の具体例を紹介します。
-
(1)募集・採用にあたって身長・体重・体力を要件とするもの
- 荷物を運搬する業務について、当該業務に必要な筋力よりも強い筋力があることを要件とする
- 単なる受付など防犯を本来の目的としていない警備員の業務について、一定の身長・体重があることを要件とする
-
(2)募集・採用・昇進・職種の変更にあたって転居を伴う転勤に応じられることを要件とするもの
- 広域にわたり展開する支店や支社がなくその計画もないにもかかわらず、転居を伴う転勤に応じられることが募集・採用の要件になっている
- 広域にわたり展開する支店や支社があるものの、転居を伴う転勤の実態がほとんどないにもかかわらず、転居を伴う転勤に応じられることが募集・採用の要件になっている
-
(3)昇進にあたって転勤経験があることを要件とするもの
- 課長に昇進するにあたって、他の地域の支店・支社での勤務経験が特に必要であるとは認められないにもかかわらず、転居を伴う転勤経験があることを要件とする
一般的に、身長、体重、筋力などは男性と比べて女性の方が低いことが多く、業務上必要な範囲を超えて、それらの条件で雇用の機会を制限することは間接的な女性差別にあたると考えられます。
また、日本では依然として育児や介護などの家庭的責任を女性が担うことが多く、転居をともなう転勤は不可能であるケースがあります。求人募集や昇進に転勤を条件にすることも、実際には性別による間接差別となり得るのです。
加えて、上記で挙げたケース以外であっても、会社が定めたルールに合理的な理由がなく労働者の能力発揮に不必要な要件とみなされる場合は、間接差別として違法と判断される可能性があるということにも留意しておきましょう。
3、間接差別の予防策
違法な間接差別を予防するためにできる対策としては、以下のようなものが挙げられます。
-
(1)募集・採用基準の見直し
直接的な男女差別とは異なり、間接差別は、一見すると性別とは関係のないようなルールや取り扱いであっても、実質的にみれば一方の性に不利益を与えるものになります。このような間接差別は、意図せずに行われているケースもありますので、まずは自社の募集や採用基準を確認し、違法な間接差別が含まれていないかどうかをチェックするようにしましょう。
違法な間接差別が含まれているまたは違法とはいえなくても不当な間接差別になり得る条件が含まれているような場合には、すぐに条件の見直しを行わなければなりません。 -
(2)教育と研修の実施
性別を理由とした直接差別であれば、違法な行為であると認識・理解している人が多いですが、間接差別についてはその内容を十分に理解していない人もいます。経営者が間接差別の違法性を理解していたとしても、現場の労働者がそのことを把握していなければ、違法な間接差別が行われるリスクがあります。
このようなリスクを排除するには、労働者の教育と研修の実施が有効な手段となります。定期的に適切な研修を実施することで、違法な間接差別の予防効果が期待できます。 -
(3)評価基準の透明化
労働者の評価基準が曖昧・不明確なものだと、労働者から間接差別の疑いをもたれてしまいます。労働者の昇進や昇給に関する条件については、できる限り明確にし、透明化することで、労働者から間接差別の疑いをかけられることを回避できます。
また、評価基準の見直しをする際には、「転居を伴う転勤に応じられること」、「転居を伴う転勤の経験があること」などの条件を設けるのは避けた方がよいでしょう。なぜなら、これらは一般的に男性のみを有利に扱う条件になりますので、違法な間接差別に当たる可能性が高くなってしまいます。 -
(4)ハラスメント防止策の強化
間接差別は、性別に関する固定観念に基づく嫌がらせや差別という「ジェンダーハラスメント」の一種と考えられます。そのため、間接差別を防ぐ対策としては、ハラスメント防止策の強化を行うことも有効な手段といえます。
社内にハラスメント相談の専用の窓口を設置するなどして、間接差別によるハラスメントの予防に努めるとよいでしょう。
4、従業員との労働トラブルは弁護士に相談を
従業員との労働トラブルは、弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)間接差別などのトラブルを未然に防げる
間接差別などの人権にまつわる問題は、労働者とのトラブルの原因になるだけでなく、発覚した場合、企業の社会的な信用の低下につながりかねません。
間接差別を予防する対策にはさまざまなものがありますので、企業の実情に応じて適切な方法を選択することが重要です。
弁護士に相談をすれば、企業が抱えている労働問題の解決に向けた最善の提案をしてもらうことができるでしょう。 -
(2)もしトラブルが起きた場合でも影響を最小限に抑えられる
労働者との間でトラブルが生じてしまうと、まずは労働者との話し合いにより解決を図ることになります。しかし、本来の業務に加えて、トラブルが生じた労働者の対応もしなければならないのは、担当者にとって大きな負担となります。
そのような場合には弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士であれば会社の代理人として労働者と交渉することができるため、担当者の負担を大幅に軽減することができます。また、法的に適正な条件で解決することができますので、もしトラブルが起きた場合でも弁護士がいれば影響を最小限に抑えることが可能です。 -
(3)法的手続きを任せられる
トラブルの内容や交渉の経過によっては、話し合いで解決することができないと、労働者から労働審判の申し立てや訴訟提起などの法的手続きへの対応が必要になります。
このような法的手続きを一般の方が自分だけで対応するのは困難ですので、専門家である弁護士にお任せください。弁護士であれば法的手続きが必要になったとしても、豊富な知識や経験に基づいて適切に対応することができます。
お問い合わせください。
5、まとめ
間接差別とは、表面上は中立的な措置に見えても、実際は特定の性別に不利益をもたらす差別のことをいいます。このような間接差別に該当する社内規定がある場合、従業員とのトラブルを招く可能性があります。
このような間接差別を防ぐためには、評価基準の透明化などの予防策を講じることが大切です。また、従業員とのトラブルを防ぐために労働問題について日頃から弁護士に相談するのがおすすめです。
ベリーベスト法律事務所では顧問弁護士サービスが定額で3980円から利用することができますので、労働問題や企業法務に詳しい弁護士をお探しの方は、まずはベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています