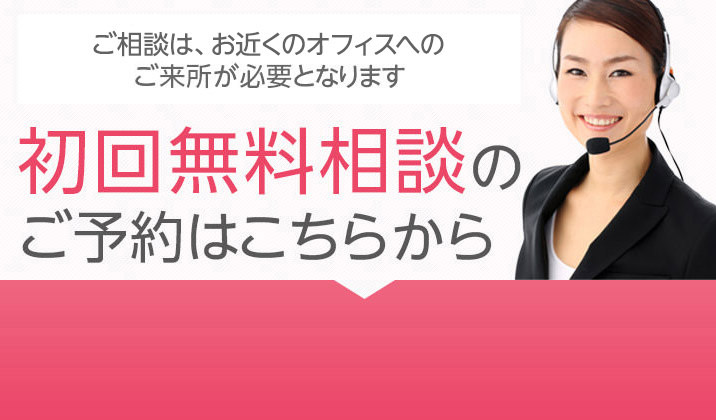すぐ怒る夫と離婚することはできる? 後悔しないための対処法を解説
- 離婚
- 離婚
- すぐ怒る夫

なにかあるたびにすぐに怒るような夫と結婚されている方は、一緒に生活することにうんざりしてしまうこともあるでしょう。
ささいなことで怒るような状態では、子どもに対しても悪影響を与える可能性もあります。そのため、夫との離婚を検討される場合もあるかもしれません。
本コラムでは、「夫がすぐ怒る」ことは離婚の理由になるかどうか、離婚する方法や離婚までの流れについて、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの弁護士が解説します。
1、すぐ怒る夫と離婚することは可能なのか
まず、すぐ怒る夫と離婚することができるかどうかについて解説します。
-
(1)お互いに合意をしていれば離婚は可能
離婚をする際には、まずは夫婦で話し合いをして、離婚をするかどうかや離婚の条件について決めることになります。
このように話し合って離婚する方法を「協議離婚」といいます。
協議離婚であれば離婚理由を問われることはないため、夫婦が離婚に合意をしているのであればどのような理由であっても離婚をすることが可能です。 -
(2)夫が離婚に合意しない場合には法定離婚事由が必要
夫が離婚に合意をしてくれない場合には、最終的に家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判所に離婚を判断してもらうことになります。
ただし、裁判によって離婚するためには、民法が定める法定離婚事由が必要となります。
具体的には、夫婦のあいだに以下のような事情が存在することが要件になるのです。- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者の生死が3年以上不明
- 強度の精神障害にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻を継続した難い重大な事由
-
(3)夫がすぐ怒ることはモラハラにあたる可能性がある
「モラハラ」とは、モラルハラスメントの略称であり、暴言や嫌がらせなどによって相手を精神的に追い詰める行為をいいます。
妻に対してすぐに怒る夫は、暴言などによって妻を精神的に傷付けている場合もあり、モラハラを行っている可能性もあります。
モラハラの程度がひどい場合には、法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
なお、家庭内でモラハラが行われている状況を子どもが目の当たりにすると、子どもが精神的に不安定になったり、感情のコントロールがうまくできなかったりするなどの悪影響が生じるおそれもあります。
子どものためにも、モラハラが行われている環境からは早めに脱出することが大切です。
2、離婚する際に取り決めること
夫と離婚をする際には、離婚をするかどうかだけではなく、以下のような条件についても定める必要があります。
-
(1)親権
夫婦に子どもがいる場合には、離婚の際にどちらか一方の親を親権者に指定しなければなりません。
基本的には、親権者に指定された親が子どもと一緒に生活することになるため、自分たちの都合だけでなく子どもにとってどちらが親権者としてふさわしいのかという観点からしっかりと検討することが大切です。
親権者をどちらにするのかについては、まずは夫婦間の協議によって決めることになります。
もし夫婦間で合意が成立しない場合には、離婚条件のひとつとして、家庭裁判所の離婚調停や離婚裁判によって決定していくことになります。 -
(2)養育費
子どもがいる場合には、離婚後の養育費についても取り決める必要があります。
親権と同じように、養育費の金額や支払い方法、支払期間などについても、まずは夫婦の協議で決めることになります。
そして、合意が成立しない場合には、家庭裁判所の調停や裁判によって決定することになるのです。
なお、養育費の金額については、裁判所が公表している養育費算定表を利用すれば一定の相場を知ることができます。 -
(3)財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚時に清算する制度のことです。
夫婦の財産形成に対する貢献度は、基本的には等しいと考えられているため、財産分与によって夫婦の共有財産の2分の1を請求することができます。
共働きの夫婦のみならず、夫が会社員で妻が専業主婦であるといった場合にも、この原則は変わりません。
なお、離婚後であっても財産分与を請求することはできますが、その場合には、離婚から2年以内に請求しなければ財産分与を求める権利を失ってしまう点に注意してください。 -
(4)慰謝料
DVやモラハラや不貞行為など、相手の側に離婚の原因がある場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料を請求する場合には、相手の側に責任があることを証拠によって立証していかなければなりません。
慰謝料を請求する場合には、証拠隠滅をされたり言い逃れたりされないように、きちんと証拠を収集してから請求を行うことが大切です。
3、夫と離婚するまでの流れ
夫と離婚をする場合には、以下のような流れで進めていきます。
-
(1)協議離婚
離婚することを決意した場合には、まずは、夫と話し合いをして離婚をするかどうかや離婚条件を決めていきます。
これを「協議離婚」といい、離婚する夫婦のほとんどがこの協議離婚によって離婚をしています。
話し合いによって離婚の合意が成立した場合には、離婚届に記入をして、市区町村役場に提出すれば離婚が成立します。
離婚の条件について夫婦間で定めた場合には、口頭による合意だけではなく、必ず離婚協議書にその内容を残しておくことが大切です。
また、養育費や慰謝料や財産分与などの金銭の支払いが伴う場合には、離婚協議書は公正証書の形式で作成しましょう。
公正証書を作成しておけば、夫が金銭債務の履行を怠った場合にも、裁判をすることなく強制執行の申し立てをして預貯金や給料といった財産を差し押さえることができます。 -
(2)調停離婚
夫婦の話し合いによって離婚の合意ができなかった場合や離婚条件がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申し立てをすることになります。
離婚調停においては、調停委員が夫婦のあいだに入って話し合いを進行するため、夫がすぐ怒ったり感情的になったりする場合でも、話し合いを進めやすくなります。
ただし、離婚調停も協議離婚と同様にあくまで話し合いに基づく手続きであるため、調停委員が介入してもお互いの合意が得られない場合には、離婚調停は不成立となってしまいます。 -
(3)審判離婚
離婚調停が不成立になった場合、家庭裁判所が調停に代わる審判によって離婚を命じることがあります。
これを「審判離婚」といいます。
審判離婚は、離婚自体に同意しているものの離婚条件にわずかな食い違いがある場合や、離婚すること自体や離婚条件に争いがないものの調停成立のための出廷ができない場合などに利用される手続きです。
ただし、審判離婚は、異議申し立てによってその効力を失うものであるため、実際にはほとんど利用されていません。 -
(4)裁判離婚
離婚調停が不成立になった場合には、最終的に、家庭裁判所に離婚裁判を起こして裁判所に離婚の可否を判断してもらうことになります。
裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由が必要になりますので、離婚を求める側としては、証拠に基づいて法定離婚事由の存在を主張・立証していく必要があります。
また、裁判離婚の手続きは煩雑であるうえに、離婚事由の立証には専門的な知識も必要になるため、弁護士に依頼したうえで進行することをおすすめします。
4、離婚問題を弁護士に依頼するメリット
以下では、離婚を決意した際に弁護士に依頼することのメリットを解説します。
-
(1)適正な離婚条件がわかる
離婚をする際には、養育費、慰謝料、財産分与などの離婚条件を決めなければなりません。養育費や慰謝料などの金額には独自の計算方法や相場があり、財産分与などにおいても考慮すべきさまざまな要素などが存在します。
弁護士に依頼をすれば、豊富な経験や知識に基づいて、個別具体的な事案に応じた適正な離婚条件を判断することができます。
そのため、不利な条件で離婚をしてしまうリスクを回避できるのです。 -
(2)相手と直接やりとりをしなくてよい
離婚をする際には、相手と話し合いをすることが欠かせません。
しかし、すぐに怒るような夫と離婚の話をしようとしても、相手が感情的になってしまい話し合いができない可能性が高いでしょう。
弁護士に依頼をすれば、相手との交渉を代行させることができます。
また、第三者かつ専門家である弁護士が交渉の窓口になることで、相手は感情的になるのを控える可能性があります。
ご自身が夫から暴言を吐かれたり怒鳴られたりする心配もなくなるため、精神的なストレスも大幅に軽減されるでしょう。 -
(3)調停や裁判になっても安心して任せることができる
夫婦の話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所の調停や裁判によって決着を付ける必要があります。
しかし、ほとんどの方にとっては家庭裁判所の手続きを利用するのが初めての経験であるため、どのように進めればよいのかなど、さまざまな不安を感じるでしょう。
弁護士には、申し立ての手続きや書面の作成や提出などを依頼することができます。
また、弁護士は調停にも同行しますので、調停委員の前でも安心して話をすることができるでしょう。
5、まとめ
すぐに怒る夫から暴言を吐かれたり、怒鳴られたりして精神的な苦痛を感じている女性のなかには、離婚を検討されている方も多いでしょう。
夫からひどいモラハラを受けている場合には、法定離婚事由に該当して、相手が離婚を拒否していても裁判によって離婚が認められる可能性があります。
夫からの暴言や暴力、モラハラなどに苦しまれている方は、離婚の手続きを進めるため、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています