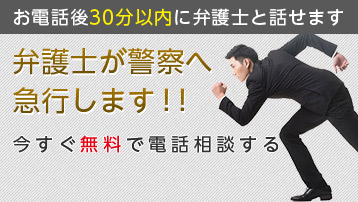貸金業法違反になるケースとは|個人によるお金の貸付は違法になる?
- その他
- 貸金業法違反

大阪府は、行政処分情報として、貸金業法違反を理由に登録取り消し処分を受けた貸金事業者をホームページで公表しています。
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者に関する規制を定めた法律です。しかし、個人間のお金の貸付に関しても、一定の条件に該当するものについては、貸金業法による規制の対象となります。したがって、貸金業法に違反して貸付を行った場合には、貸金業者はもちろん、個人にも罰則が適用されるおそれもありますので注意が必要です。
今回は、貸金業法違反に該当するケースや個人による貸付の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの弁護士が解説します。


1、貸金業法とは?
貸金業法とはどのような法律なのでしょうか。以下では、貸金業法に関する基本事項について解説します。
-
(1)賃金業法の目的
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借入について定めた法律です。
近年、消費者金融などの貸金業者から返済できないほどの借入を繰り返してしまう、いわゆる「多重債務者」が増えています。多重債務の状態に陥ると正常な生活を送るのも困難な状態になってしまうことから深刻な社会問題となっていました。
貸金業法は、このような多重債務問題を解決することを目的として、貸金業の適正化、過剰貸付の抑制、金利の適正化、闇金対策などの観点から規制を行っています。 -
(2)賃金業法の概要
貸金業法では、主に以下のような規制を行い、利用者の利益を保護しています。
- ① 総量規制
総量規制とは、貸金業者などから借りることができるお金の総額を制限する規制です。
具体的には、貸金業者などからの借入残高が利用者の年収の3分の1を超える場合に、新規の借入ができなくなるというものです。貸金業者から年収を証明する書類の提出が求められるのは、返済能力を判断するという意味だけではなく、総量規制に違反しないかを判断するという意味もあります。
- ② 上限金利の設定
利息制限法では、貸付額に応じて15~20%までの上限金利が定められています。上限金利を超える金利での貸付があった場合には、無効となり、貸付を行った貸金業者に対しては行政処分が下されます。
以前は、貸金業法の上限金利と出資法の上限金利が異なっていたため、両者の間にはいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利帯が存在していました。しかし、その後の出資法改正により出資法の上限金利が29.2%から20%へと引き下げられたため、グレーゾーン金利は撤廃されることになりました。
- ③ 貸金業者の規制
貸金業を営むためには、財務局長または都道府県知事に申請をし、貸金業登録を受ける必要があります。貸金業登録を受けるためには、純資産額が5000万円以上、一定数の貸金業取扱主任者の配置などの厳しい規制があります。
また、違法な取り立てから債務者を保護するために、取立規制なども貸金業法で定められています。
- ① 総量規制
-
(3)貸金業法に違反した場合の罰則
貸金業法違反の種類には、主に、無登録営業、高利貸し、不当な取り立てなどがあります。
それぞれの規制に違反した場合の罰則は、以下のとおりです。- 無登録営業:10年以下の懲役もしくは3000万円以下の罰金またはこれらの併科
- 高利貸し:5年以下の懲役、1000万円(法人は3000万円)以下の罰金
- 不当な取り立て:2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科
2、貸金業法違反に該当するケース
貸金業法違反となる代表的なものとしては、以下のケースが挙げられます。
-
(1)無登録で貸金業を行った
無登録で貸金業を行うことは貸金業法違反となります。
貸金業を営む場合には、貸金業法により国または都道府県への登録が義務付けられています。無登録での貸金業を許してしまうと、不正な取引やトラブルが生じる原因となりますので、貸金業法によって規制されています。 -
(2)高額な金利で貸し付けた
上限金利を超える利息を取ることは、貸金業法によって禁止されていますので、貸金業法違反となります。
貸金業法では、借入額に応じて、以下のような上限金利が定められています。- 10万円未満:年利20%
- 10万円以上100万円未満:年利18%
- 100万円以上:年利15%
-
(3)過剰な取り立てを行った
貸金業法では、貸金業者が消費者に対して、暴力、脅迫、名誉毀損などの不法行為をすることを禁止しています。そのため、過剰な取り立てがあった場合には、貸金業法違反となります。
具体的には、以下のような行為が貸金業法の禁止する過剰な取り立てにあたります。- 債務者やその家族などに暴言や暴力をふるう
- 債務者やその家族などに嘘や誇張した内容を伝える
- 債務者やその家族などに無断で訪問する
- 債務者やその家族などに不当な支払い方法を要求する
-
(4)従業者が身分証明書を携帯していない
貸金業法では、貸金業の従業者に対して、身分証明書の携帯を義務付けています。これは、取り立てなどを行う従業者の身分を明らかにするとともに、債務者への強引な取り立てを抑制する目的の規制になります。
従業者が身分証明書を携帯していなかった場合には、貸金業法違反となります。 -
(5)暴力団員などを従事させる
暴力団員などを貸金業に従事させた場合には、貸金業法違反となります。暴力団員などが貸金業を営むことは、違法な取り立てを助長するおそれがあり、違法な組織の資金源になるおそれがあることから、貸金業法によって禁止されています。
お問い合わせください。
3、個人による貸付を行う場合の注意点
個人による貸付を行う場合には、以下の点に注意が必要です。
-
(1)個人による貸付は貸金業法違反になるのか?
貸金業法は、貸金業を営む者による貸付行為などを規制する法律ですので、原則として個人による貸付は、貸金業法違反とはなりません。
しかし、個人がお金の貸付をする場合でも、反復継続する意志を持って貸付を行う場合には、貸金業法上の「貸金業」に該当します。このような場合には、個人であっても国や都道府県への登録が必要になり、無登録での貸付を行えば貸金業法違反となります。
家族や友人などにお金を貸す程度であれば問題はありませんが、広く第三者へのお金の貸付を勧誘してしまうと貸金業とみなされるリスクもありますので注意が必要です。 -
(2)個人間融資では「出資法」の上限金利に注意が必要
個人間の融資では、出資法の上限金利にも注意が必要です。
出資法では、貸金業者からの借入だけではなく、個人間の借入についても上限金利の規制があります。個人間での融資の場合には、年利109.5%を超えて貸付をした場合には出資法違反となります。おおよそのイメージとしては、1か月で1割程度の利息を取ってしまうと出資法違反のおそれがあります。
このように出資法の上限金利に違反して貸付を行った場合には、出資法違反となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはそれらが併科されます。
4、個人でお金の貸し借りをする際には書面を残すことが大切
貸金業法上の規制はクリアできたとしても、個人間のお金の貸し借りではトラブルが起こりがちです。泣き寝入りしないためにも、貸付する際のポイントを押さえておくことが大切です。
ポイントのひとつ目は、貸し借りが明確にわかる書面を残しておくことです。個人間の貸付では、お互いの関係性から借用書を作成することなく、口頭でのやり取りだけで済ましがちです。しかし口頭だけでは、貸付の事実や条件などが不明確になり、後日トラブルになる可能性があります。借用書という格式張った書面でなくとも、必ず書面を残しておくことが大切です。
ふたつ目は、個人間の貸付であっても利息を付けることを検討する、ということです。お金を貸す行為は、貸す側にとって回収不能などのリスクがあります。利息を付けた貸付はひとつのリスクヘッジになり得ます。利息を付ける場合にも、利率などの条件を書面に記載しておくようにしましょう。
個人間の貸付では、さまざまなトラブルが生じるおそれがあります。将来のトラブルを回避するためにも、個人間での貸付をお考えの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。また、すでに返済が滞るなどのトラブルが生じているという場合も、債権回収の方法についてアドバイスができますので、弁護士に相談するようにしましょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
貸金業法は、貸金業者を対象にした法律ですので、個人間の貸付が貸金業法違反となることは基本的にはありません。しかし、個人間の貸付であっても出資法の上限利息を守ること、借用書などの書面を作成することなどいくつか注意すべきポイントがあります。
貸金業法は、多重債務から利用者を守るために貸金業者に対して、さまざまな規制を行っています。お金の貸し借りに不安がある場合は、ひとりで対応するのではなく、弁護士に相談することでトラブルの深刻化を防げるでしょう。
貸金業法違反の容疑で警察から連絡がきたケースや、個人間でのお金の貸し借りでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています