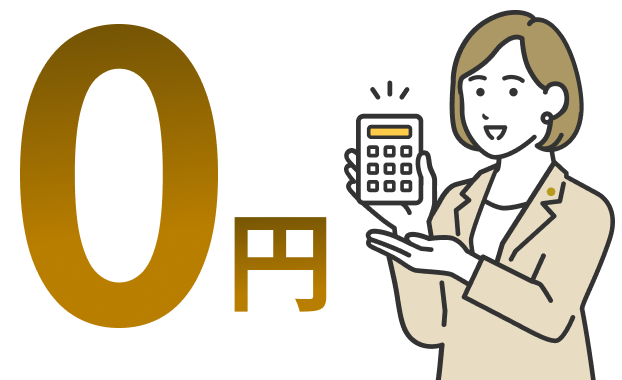祖父死亡の遺産相続|孫が相続できるケースと注意点を弁護士が解説
- 遺産を残す方
- 祖父死亡
- 相続
- 孫

祖父が亡くなった際、孫は一般的に遺産相続の対象にはなりません。しかし、祖父として孫に遺産を渡したいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この場合、遺言書や養子縁組などの制度を利用することで、例外的に孫が相続人にできるケースがあります。また、生前対策を行うことで財産を承継させるのもひとつの手段です。
本コラムでは、孫が祖父の遺産を相続できるケースや有効な生前対策・注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの弁護士が解説します。


1、祖父死亡の遺産相続で、孫は祖父の相続人になれる?
祖父が亡くなった際、その遺産を相続するのは原則として「法定相続人」ですが、孫は祖父の法定相続人に含まれません。
法定相続人とは、法律で定められた順序にもとづいて遺産を受け取る権利をもつ人物です。
民法では、被相続人(亡くなった人)の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の親族は以下の順位で法定相続人となると定めています。
| 法定相続人の順位 | |
|---|---|
| 第一順位 | 子 |
| 第二順位 | 直系尊属(父母・祖父母) |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 |
上記の通り、孫は法定相続人には入っておらず原則として直接的な相続権はありません。
被相続人の孫が相続人になれるのは特定の条件を満たす場合のみであると、理解しておく必要があります。
2、例外的に孫が祖父の遺産を相続できる3つのケース
例外的に孫が祖父の遺産を相続できるケースとは、どのような状況なのでしょうか?以下では、被相続人の孫が遺産を相続できる3つのケースを解説します。
-
(1)祖父が孫に遺言を残しているケース
祖父が孫に遺言を残しているケースでは、孫が対象の財産を相続できます。被相続人の遺言書が残されている場合は、原則として法定相続分による遺産分割よりも遺言書の内容が優先されるためです。
たとえば、遺言書に「孫に不動産を遺贈する」と記載されていれば、法定相続人ではない孫でも不動産を相続できます。
ただし、遺言書であっても、遺留分(いりゅうぶん)の侵害を主張されたら拒むことはできません。遺留分とは、一部の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分です。
遺言書を作成する際は、相続トラブルを避けるためにも遺留分の侵害に注意する必要があります。 -
(2)祖父と孫が養子縁組をしているケース
祖父と孫が養子縁組をしている場合、孫は祖父の法定相続人となります。養子縁組をすると法律上の親子関係が生じ、孫は祖父の子どもと同等の存在として扱われるためです。
養子の相続分は、実の子どもの相続分と同じです。たとえば、配偶者がなく、実の子どもがふたり・養子がひとりいた場合は、相続財産を3等分することになります。
養子縁組をするには、市区町村の役所で手続きが必要です。祖父が亡くなり相続が開始した時点で養子縁組が成立していない場合は、法定相続人として認められないため注意しましょう。 -
(3)孫がすでに死亡している親の代襲相続人になるケース
孫が祖父の遺産を相続できるもうひとつのケースは、孫が代襲相続人になる場合です。代襲相続とは、法定相続人となるはずの人物がすでに亡くなっている場合に、その子どもが代わりに相続人となる制度です。
たとえば、祖父よりも先に子どもが亡くなっている場合、亡くなった子どもの相続分はその子ども(孫)が受け継ぎます。
代襲相続が発生すると相続手続きが複雑化しやすいため、弁護士に相談しながら進めていくことをおすすめします。
お問い合わせください。
3、生前対策|祖父が孫に財産を承継するための4つの方法
祖父から孫へ確実に財産を承継させたい場合は、生前からの計画的な対策が重要です。相続や遺贈以外で財産を渡す4つの方法について、以下で確認していきましょう。
-
(1)祖父が孫に生前贈与をする
生前贈与とは、存命中に自分の財産を他者に無償で贈る方法です。生前贈与は誰に対しても行えるため、孫に財産を贈与することも可能です。
贈与する財産の金額に制限はありませんが、一定額を超えた場合は贈与税を支払う必要があります。受贈者(贈与を受ける方)ひとりあたり、年間110万円以内の贈与であれば基本的に課税はされません。
ただし、場合によっては、3年前(改正に応じて7年前)までの孫に対する生前贈与は相続財産に持ち戻されるケースがありますので、早い段階から慎重に、計画的に行うことが重要です。 -
(2)教育資金として孫に財産を贈与する
教育資金贈与の特例を活用すると、受贈者ひとりあたり最大1500万円までの教育資金を非課税で贈与できます。特例の対象となるのは、入学金・授業料・塾の月謝・入園料・保育料・留学費用など教育にかかわるさまざまな費用です。
受贈者の要件は、前年の所得が1000万円を超えていない30歳未満の子どもや孫です。祖父から孫に対する贈与にも適用されるため、教育関係の資金を一括で渡したい場合は検討してみてください。
なお、教育資金贈与の特例を利用できる期間は令和8年3月31日までとなっているため注意が必要です。 -
(3)孫を受取人とする生命保険に加入する
祖父から孫に財産を渡す方法として、孫を受取人に指定した生命保険に加入するのもひとつの手段です。
生命保険金は原則として遺産分割の対象にならないため、受取人である孫の固有財産として扱われます。
ただし、法定相続人ではない孫が生命保険金を受け取る場合は、相続税の非課税枠が適用されません。孫が高額の相続税を支払わなくてはならなくなる可能性もあるため、注意しておく必要があります。 -
(4)死因贈与を行う
死因贈与とは、贈与者が亡くなった際に、あらかじめ指定した財産を受贈者に贈与することを約束する方法です。遺言書による遺贈と似ていますが、死因贈与は生前の契約によって成立する贈与であるため、祖父と孫の間で合意が必要となります。
死因贈与は口約束だけでも成立しますが、相続開始後のトラブルを防ぐためには贈与契約書を作成しておくことが望ましいです。
また、死因贈与も相続税の課税対象となるため、税負担は事前に確認しておくようにしましょう。
4、孫が祖父の財産を承継する場合の3つの注意点
孫が祖父の財産を承継する場合に、押さえておくべき注意点が3つあります。
以下、ひとつずつ解説していきます。
-
(1)他の相続人とトラブルに発展するリスクがある
孫が祖父の財産を承継する際、他の相続人との間でトラブルに発展するリスクがあります。
とくに、法定相続人ではない孫が遺産を受け取る場合は他の相続人の取り分が減るため、相続人が不満を感じるケースもあるでしょう。
トラブルを防ぐためには、財産分配の意図や背景を事前に相続人全体に説明しておくことが有効です。孫に財産を渡したいという意思を明確に伝えたり、事前に弁護士に相談してトラブル防止策を講じたりすることで、不要なトラブルを避けられる可能性があります。 -
(2)遺留分侵害額請求を受けるリスクがある
承継する財産の金額によっては、孫が「遺留分侵害額請求」を受けるリスクもあります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている最低限相続できる遺産の割合です。遺言書による遺贈や生前贈与で遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求による遺産の取り戻しができます。
遺留分侵害額請求が認められると、孫は相続した財産の一部を金銭で返還しなければなりません。孫に財産を渡す際は、他の相続人の遺留分を考慮した上で適切な分配計画を立てる必要があります。 -
(3)相続税が2割加算されるケースがある
孫が祖父の財産を相続した場合、相続税が通常よりも2割分高くなる可能性があります。相続では、被相続人の配偶者・父母・子ども以外が相続する場合に、相続税額に2割加算するというルールがあるためです。
具体的には、主に以下の方が相続税額の2割加算の対象となります。- 被相続人の配偶者・父母・子ども以外で相続または遺贈によって財産を取得した方
- 被相続人と養子縁組した被相続人の孫で、被相続人の実子がまだ存命の方
子どもの代襲相続人となる孫については2割加算の対象外ですが、養子縁組をした孫は2割加算の対象になるケースがあります。祖父の財産を孫に相続させる際には、相続税の負担についても考慮するようにしましょう。
5、まとめ
法定相続の原則では被相続人の孫が相続人となるケースはまれですが、特定の条件や生前対策によって財産を渡すことは可能です。しかし、祖父から孫に財産を承継する場合、意図せぬトラブルや税負担が発生するリスクがあります。
トラブルを避けるためには、財産分配の意図を明確にし、相続人全体の理解を得ておくことが重要です。また、事前に法律や税制のルールを把握した上で、最善の方法を選択する必要があります。
相続に関する問題は複雑でケースごとに対応が異なるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
当事務所には、相続問題の実績が豊富な弁護士が在籍しています。祖父の遺産相続や孫への財産承継についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています